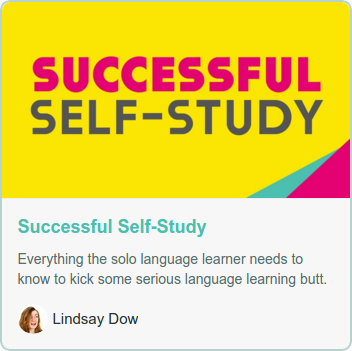Natural speed please
落日が平原の果てを染めている。朱よりも血の色に近かった。虚空《こくう》でごおごおと風が唸り、足首までも覆い隠す丈の高い草の海を横切っている狭い街道の上で、今しも一頭の馬とその騎手が、真正面から吹きつける風威の壁にさえぎられたかのごとく歩みを止めた。
道は二十メートルほど前方でやや昇り気味となり、そこを昇りつめれば、この辺境地区《セクター》の一小村「ランシルバ」の家並みと緑の田園地帯とが望めるはずであった。
そのゆるい傾斜の上がり口に、ひとりの少女が立っていた。
馬は、その風体に驚いて停止したのかもしれない。大柄で、燃えるような瞳の美少女であった。あさ黒く陽灼けし、黒髪を後ろで束ねている。荒野に生きるもの特有の、荒々しい野性の気が全身から発散していた。夏の光みたいな美貌からして、ひと目彼女を見たものは、すべからく、首から下の曲線《カーブ》に注目するであろうのに、すり切れた青いスカーフを巻いた首の下は、くるぶしまで灰色の防水ケープに覆われていた。ネックレスも首輪も、女を感じせる装飾品はまるで身につけていない。革製の密着《フィット》サンダルと、右手に束ねた黒い鞭《むち》らしき品を除いては。