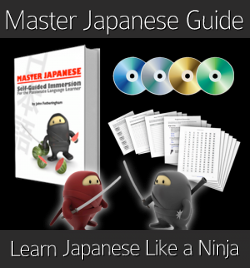slow/natural speed please
高校生のころ、私は小さな村から町の高校まで汽車で通学していました。町までは、たった二両編成の汽車が単線の線路を走っていました。
広い田んぼの中にポツンと小さな駅が建っていて、駅前には柱もベンチも古びて黒光していました。たった一つのホームへと続く改札口は、木の柵のような形をしていて、一時間に一本しかない汽車が近づいたときだけあけられました。改札口の上に駅員さんが行き先を書いた札をかけながら、「お待たせしました。〇〇行きの改札です。」というと,待合室の人々がぞろぞろと並び始めるのでした。
町には高校がいくつかあったので、朝の駅は大急ぎで自転車を止めて駆け込んでくる学生たちであふれていました。私は毎朝少し早く来て、ある人の姿が見えるのを今か今かとまっていました。彼は私とは別の高校の一年先輩で、話をしたこともなかったのですが、なぜか気になって仕方がなかったのです。特にハンサムではなかったけれど、ちょっと背が高くて、夏の制服の白いシャツが素敵でした。彼はいつもぎりぎりに来たので、私は先にホームに出て改札口のほうを振り返りながら、「あの人が私の隣に来て『おはよう』といってくれないかなあ。」「でも、もし本当にそうなったらどうしよう…。」などと考えていました。
ある朝私は朝寝坊をして、駅に着いたときにはもう近づいてくる汽車の警笛が聞こえていました。あわてて自転車置き場に自転車を止めているとき、隣にすっと入ってきた自転車は彼のだったのです。私はびっくりしてどきどきしてしまいました。「おはよう。」彼が言いました。「おはよう…ございます…。」私は声は声になりませんでした。急いで改札を通って、一番後ろのドアから汽車に飛び乗りました。私は何か話したかったのですが、何をどう話していいかわからなくて黙っていました。彼も緊張しているのか、私のことなど無視しているのか、黙っていました。汽車の中の人々の目が、私たち二人を見ているような気がしていつもたってもいられませんでした。汽車が町についたときにはがっかりしてなきたいような、それでいてほっとしたような気持ちでした。彼と私はちょっと目で挨拶して、それぞれ別の方向へ降りて行きました。次の日からはなぜか駅で彼と一緒になることはありませんでした。
しばらくして、彼が東京の大学に進学したことを人から聞きました。私も次の年に隣の県の学校に進学して村を離れ、そのままそこに残って就職しました。このごろからの便りでは、あの単線は一昨年廃線になってしまったそうです。汽車が来なくなった線路に雑草が生い茂り、小さな駅舎だけがひっそりと建っているそうです。