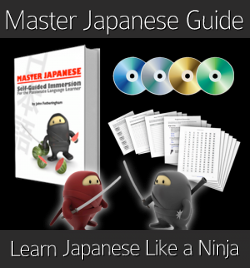京都大学と日本IBMは、数百万台もの車両が複雑に影響しあう大都市圏の広範囲な交通を、車両一台一台の動きまでミクロにシミュレートする大規模マルチエージェント交通シミュレーションシステムを共同開発しました。
未来の交通社会のシミュレーションとは何なのかを、京都大学情報学研究科の石田亨(とおる)教授と、日本IBM東京基礎研究所の加藤整(せい)研究員にお話をうかがいました。
あのう、大規模なマルチエイジェントのシミュレーションということをやろうと思いますと、大きくふたつの技術が必要になります。一つは、人間をモデル化して個々のエージェントを作る。で、これは京都大学が長い間研究をしていました。で、もう一つは、そうやってモデル化したたくさんのエージェントを、まあ百万に及ぶようなエージェントをシミュレーションするようなサーバー、エージェントサーバーといいますが、それが必要になります。
で、IMBの東京基礎研究所さんの方では、すいぶん長い間、そのエージェントサーバー、大規模シミュレーターの研究をされていまして、国際会議なんかでも多数発表されていて、まあ、有名だったんですね。で、わたくしども、ひょっとしたら、IBMさんといっしょにやると、こう、ふたつの技術が組み合わせることができる。エージェントをモデル化して、そして大規模にシミュレーションすることができる。で、これはひょっとすると面白い研究が始まるんじゃないかと思って、お願いをしたというのが背景です。
ええと、まあ、今回数百万台規模の車両を同時にシミュレーションするってことを可能にしたんですけども、ええと、その技術的背景は三つあります。まず一つ目は、われわれ東京基礎研究所で、1990年ごろですね、あの、ベルシステム向けの、その、ハイボリュームなトランザクションを処理するための技術ってものを築立(?)しました。でまあ、この、ええと、大規模なトランザクション処理のための技術を、ええ、今回ですね、あの、エージェントシミュレーションのために適用したということです。
二つ目は、その、近年、PCクラスタ環境というものが、盛んになってきてるんですけれども、その、その環境の下でですね、複数計算機、まあ大量の、例えば数百台とか数千台規模のPCの上で、同時にシミュレーション、交通のシミュレーションを行えるような環境を作った、開発したと。で、それが二つ目です。
三つ目はですね、あの、われわれの東京基礎研究所の研究員がですね、ええ、まあ性能をあげるために、プログラムをチューニングして、大規模に出来るようにしたということで、これらの三つによって、数百万台、数千万台の車両を同時にシミュレーションすることが可能になったということです。
これからの日本っていうのが、高齢化していくというのが、みなさん、よく知っていることだと思うんですね。で、高齢化した社会で、どういう交通行動が生じるのかということが実はあまりよく分かっていません。
例えば、高速道路ですけども、お年寄りがたくさん運転するようになると、大渋滞が発生するかもしれません。発生しないかもしれません。発生するとしたら、どういう対策をとればいいのかということも、よく分かっていません。で、また少子高齢化になりますと都市の形も変わっていくだろうと言われています。ええ、コンパクトシティというような言葉もありまして、もう一度、あの、生活が都市の中心に回帰していくだろうというようなことも言われています。
で、そういう複雑な、あの、将来の予測と、交通行動の予測というのに、恐らくこのシミュレーションを使っていけるだろうと。で、同時に環境問題も非常に大きな問題としてクローズアップされていますが、このシミュレーターを使いますと、CO2の排出量ですとか、それをどのような政策をたてると、それがどの程度削減できるとかですとか、きめ細かなシミュレーションができますので、少子高齢化、環境問題等の解決に、まあ、少しでも役に立ってくれるのではないかと期待しています。
今回、京都大学と日本IBMの共同開発した交通シミュレーションは、多くの自治体の交通都市計画によって、役立たせることができるでしょう。人間の行動を考慮して、未来の交通シミュレーションを実現する。そんな時代はもうそこまで来ています。